クルマお遍路旅一回目 実行四日目 6月11日(火)午後のお話しをします。
22話 記事全道程(Google My Maps)
この記事で分かること
ここから続く二つの札所、すなわち二十番の鶴林寺(かくりんじ)とその次の二十一番太龍寺(たいりゅうじ)は徳島県最後にして最大の難所であり、徳島 第2の「遍路ころがし」と呼ばれています。20番鶴林寺および周辺の詳細情報と、道を間違えて苦戦する21番太龍寺への紀行を詳しく読むことができます。
第二十番札所 鶴林寺(かくりんじ)
ランチを食べた立江町の「キッチンゑみ」(Map 地点A)を出発して県道を山へ(西へ)向かいます。しばらく走ると、舗装こそされているものの、細い山岳林道になってきました。
20番鶴林寺 基本情報
かくりんじ
宗派:真言宗高野山派
山号:霊鷲山(りょうじゅざん)
院号:宝珠院(ほうじゅいん)
場所:Map 地点B
アクセス
・カーナビ設定( 簡単 )
「20番鶴林寺」or 電話番号 検索でOK。
・前札所からの道( 少しハード )
「19番立江寺」から17km、県道16号線から細い山岳林道へ。ナビや標識に従えば迷わないが、アプローチは狭い急傾斜葛折り道。 🅿️無料。
・🅿️からの境内アプローチ( ハード )
🅿️から山門まではすぐ。山門からは急傾斜地に諸堂が分散。本堂までは長い石段(徒歩4分)。鐘楼・三重塔は別の石段を登る必要あり。大師堂と納経所までは山門からフラット。
お寺の種類
| 区分 | 市街区 | 田園区 | 海浜区 | 森林区 | 岩崖区 |
| 平地寺 | |||||
| 傾斜地寺 | |||||
| 山岳寺 | ○ |
宿泊事情
・宿坊あり(休館多し、要確認)。
・付近は旅館等なし。阿南市街に降りればホテル/旅館あり。(15〜17km)
・車中泊場所は、「道の駅 ひなの里かつうら」(13km)あり。隣接して「RVパークライトひなの里かつうら」(2台のみ、要予約)あり。
20番札所 紀行
札所近くは激しい葛折りの連続です。車にすれ違いをさせるための“待避所”もほとんどありません。しかもとても急傾斜です。
幸い、往きの上りの山道では、対向車に出会うこともなく、山門近くの駐車場(Map 地点B)までたどり着くことができました。
時刻は12時50分。
ここから徒歩で山を登らなければならない覚悟はありましたが、駐車場からほど近いところに山門があり少しほっとします。
20番札所は 鶴林寺(かくりんじ)というお寺です。ここの山門は、これまでの札所の中で、最も大きく荘厳に感じました。一礼してくぐるときには圧倒されます。背の高い木々に囲まれて異様な威風を放つゾクゾクするような門でした。
そして延々と上に伸びる石段です。一段一段踏みしめながら登りました。登り切ると、巨木に囲まれた荘厳な境内が広がります。
二重ではなく三重の塔になっている多宝塔は、これまでのお寺の中では初めてです。
当前ではありますが、この鶴林寺を初めとする山岳札所の多くに、高野山霊場を彷彿とさせる雰囲気を感じます。




↑ 徳島県の中でも指折りの山岳札所「鶴林寺」 威厳に満ちた佇まいに圧倒される
天気はいよいよ晴れてきて、気温も結構上がってきました。
大きな木々の間から青空が覗きます。森の緑が一層キラキラ輝いて見えます。非常に気持ちの良い時間を過ごすことができました。ゆっくりお参りし、二十番鶴林寺の駐車場を出たのは午後1時20分頃だったと思います。
「対向車さん来ませんように!」と祈りながら細い急峻な下り坂を下っていきますが、祈りむなしくデカいのが下から来ちゃいました。
見るとバスです。しかも、あの大阪集団お遍路さんの例のバス!
この人たちとは『つくづく縁があるものだ・・・』と、半分嬉しくも少々複雑な思いがしました。向こうさんも同じようなことを思っていることでしょう。
ツアーですからお客さんを乗せて入って来ざるを得ないとはいえ、この細い林道にバスが入ってくるのですから、すごいものだなと思いました。
幸いにも、バスと自分のSOLIOが出くわした下り坂はたまたま直線で、すぐ後ろには待避スペースがありました。自分が少し後ろに下がれば、幅員がちょっとだけ広がっています。
私は迷いなくギアをバックに入れて、自分の車を左に寄せながら、そこまで下がりました。
バスの運転手も今や、私の茶色メタリックの横浜ナンバーソリオはよく知っています。挨拶のクラクションと右手を上げながら、ソリオの右サイドミラーから多分10センチと離れていなかったと思いますが、すれすれのところを躊躇なく綺麗にすり抜けていきました。手慣れたものです。感心しました。
帰りの下り坂の対向車両は、このバス1台で、他にはありませんでした。
第二十一番札所 太龍寺(たいりゅうじ)へのヤバい道
そして山道を下ること20分、広々とした那珂川に出ます。しばらくはこの那珂川に沿って県道19号線を下流(東)へ走り、そして太龍寺山の北側斜面の山道を再び登ることになります。那珂川沿いの県道19号は、とても整備された立派な県道で走りやすかったです。悠々と流れる那珂川をはじめ、広々とした川沿いの風景はとても清々しく気持ちがよかったです。



↑ 那珂川にでると急に視界がひらける… 左が下流、右が上流
ただしかし、ここで私は、勉強(情報)不足による致命的な道の間違いを犯してしまいます。
二十番鶴林寺と二十一番太龍寺は、直線距離では7〜8キロ程度しか離れていません。ただし、鶴林寺から標高差500m下の那珂川まで下り、そして今度はまた太龍寺山山頂まで500m以上の標高差を登るという高低差の激しい移動となります。これが第二の「遍路ころがし」と言われる所以であり、道のり(移動距離)は直線距離の倍近くに膨らみます。
(ここからは後で知った話ですが・・)20年以上前に、那珂川上流部ちょうど太龍寺山の南側にあたる那珂川町の河川敷に「鷲の里」という道の駅と、そこを駅として太龍寺山山頂まで西日本でもっとも長い(3km弱の)ロープウェイが実は建設されていました。
道の駅「鷲の里」から太龍寺山山頂(太龍寺)までのロープウエイの所要時間はたったの10分です。
そうなのです。今や、歩きお遍路の方たちも、車お遍路の人たちも、ほとんどの参拝客は、このロープウェイを使って南側の斜面で山頂の二十一番太龍寺(たいりゅうじ)まで向かうのです。
「鷲の里ロープウェイ駅」は、那珂川の上流部、太龍寺山の南側にありますので、鶴林寺から那珂川に下ったところの県道19号線は、本当は右折して上流へ向かうのが正しいルートでした。右折して上流へ向かってさえいれば、6キロ程度で「鷲の里ロープウェイ駅」に着いていたのでした。
ルートの詳細はともかく、「少なくともロープウェイが設置されていることさえ分かっていれば」、カーナビの目的地を「鷲の里ロープウェイ駅」にすることができたはずです。
ところが、わたしは単純に「二十一番太龍寺」そのものを“目的地”にセットしてしまったために、カーナビは愚直にこの北側の斜面を登る山道を選択し、那珂川へ出たところの県道19号を下流へと左折してしまったというわけです。(痛恨の左折ミスをした分岐点:Map 地点C)


↑ 左:よく見ればGoogle Mapにもロープウェイは表示されてる 右:間違って入りこみ、徐々に怪しくなっていく道
那珂川を左折し気持ちよく下流に向かってクルマを飛ばしているときの私は、この事実を知るよしもありません。道はやがて気持ちのいい県道を離れ、太龍寺山北側山麓に向かって怪しい道へ入っていくことになります。
こちらの(間違えた)ルートは移動距離だけで15キロ以上あり、細く険しい林道を散々登らされた挙句、駐車場と言えるか疑わしい「行き止まりの広場」から、さらに1キロ以上”徒歩”で山を登らなければなりませんでした。^^;)
交通量はなく幅員も狭まっていきます。ナビには沿っているのですけれども、どうも様子がおかしいなと思っていると「この先ロープウェイには行けません。」的な看板が一度ならず何度も連続で出てきます。
そのうち「右折→”大“竜”寺” 登山道入口」という看板が出てきました。しかも「県立自然公園」(?)
『 ”大”の字も”竜”の字も微妙に違うし、”県立自然公園”とかも聞いてないし、そもそも散々出てくる「ロープウェイ」って一体なんなんだ(?) 』
なんだかすべてが釈然としません。(~_~;)

↑ 釈然としない看板が不安をそそる
「車両進入禁止」とは出ていませんが、やはり「この先ロープウェイはありません」とまたしつこく言われました。
カーナビは平然と「ここを右折して入れ」と指示します。解せない気持ちと嫌な予感を、グッと胸にしまって、その登山道へ入っていきます。(Map 地点D)
その道には同向も対向も、なにしろ一台の車もいません。細い山道をSOLIO1台で登り始めました。
『果たして本当に車が入っていい道なんだろうか?』と思うほどのただの山道です。道の細さ、勾配のきつさ、つづら折りの激しさは、鶴林寺へ向かう道の比ではありません。
待避所も無いので対向車が来たら、2台とも立ち往生間違いなしです。
※ロープウェイができてからは皆さん南側の道に行きますから、ここ20年以上は明らかに使用頻度が落ち、、だんだん朽ちた林道になってきてしまっているのでしょう・・・。


↑ どんどんヤバくなっていく道
連続する葛折りを登っていくと、1回のハンドル操作では曲がりきれないようなU字カーブもあります。見るからに古い看板があり、「この先、曲がり切ることができないので、傾斜に気をつけて一度切り返しをしてから曲がって行ってください!」みたいなことが、ご丁寧に書かれているところさえありました。
これまでの札所巡りで経験した中では最も難儀な山道でしたが、やっとの思いでお寺の駐車場というか、”ただの行き止まり”みたいなところへ到着します。
時刻は午後2時半を超えていました。
不思議なことに・・・、1台だけ、普通の白い乗用車が停まっていました。決してSUV的なオフロードを走るようなタイプの車ではなく、ホントにごく普通の乗用車なのです。

↑ 駐車場というよりは登った先の行き止まりの広場 一台だけ白い普通の乗用車が、、、
私がソリオを少し離して停め、エンジンを切っていると、、、白髪のジャケット姿の老人が近づいてきて、
「よく、こちらを登って来られましたね・・・」と声をかけてきました。
・・・
つづきは次回、太龍寺の体験だけを特別編としてお話しします。23話 第二十一番札所 太龍寺 特別編 (徳島阿南市) お楽しみに・・・
サイト内別カテゴリーへのリンク
本記事(22話)は「車中泊旅記録カテゴリー」に属しています。他カテゴリーをご覧になりたい方は、以下をご参照ください。
・「車中泊クルマ探し」カテゴリー最初の記事 →
・「車中泊旅準備」カテゴリーはここから →
・「車中泊旅記録」カテゴリーは以下から →
>16話 クルマ遍路旅 -東名高速 西へ(実行初日)- (第一回区切り打ち遍路旅)
>30話 クルマ遍路旅 -高知市〜土佐市- (第二回区切り打ち遍路旅)
>37話 クルマ遍路旅 -第三回区切り打ち開始- (第三回区切り打ち遍路旅)
>46話 早春3月の関東旅1日目 奥多摩〜甲州(遍路以外の車中泊旅)
・「車中泊旅レビュー」カテゴリーは →
>29話 クルマ遍路旅 -一回目のレビュー-(第一回区切り打ち遍路旅のレビュー)
>36話 クルマ遍路旅 -第一回第二回のまとめレビュー- (一回目二回目遍路旅のまとめレビュー)
>43話 クルマ遍路旅 第三回目のレビュー(最後の区切り打ち遍路旅のレビュー)


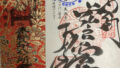
コメント